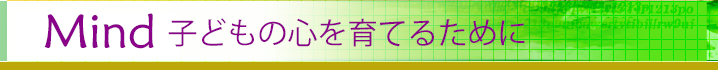子どもの意欲について 佐々木正美
■子どもの意欲はどう育つ?
きょうは、「子どもと意欲」について、話をしていきたいと思います。子どもが意欲的になるのはどういうときでしょうか。子どもがいちばん子どもらしい健康な意欲を出しているときというのは、仲間と好きなことに熱中しているときなんですね。ひとりで何かに熱中しているのは、それほど意欲的になれないんです。
例えば、夢中になってゲームをしているというのは、本当に意欲的にはなれません。私たちがこうして皆さんと話しあっていく時にいちばん大切にしていることは、人と生き生きと共感的に交わりながら社会人としての人格をどう育てていくか、という筋道をはずなさいで物事を考えていくことですね。そういう中で、人間が意欲的になるとはどういうことか、ご一緒に考えていきたいと思います。
●仲間と共感しあうときに意欲的になる
気のあった仲間と、何かに夢中になって取り組んでいるとき、子どもはいちばん意欲的になります。何かに希望をもったり、期待をもったりして胸をふくらませるときに。ですから、仲間と一緒の自由時間を与えるのはいいわけですよね。でも、意欲的でなくなった人にいくら自由時間を与えてもだめなんです。フリーターなどは自由時間ばかりですが、いくら時間がたっぷりあっても本当の意味で意欲的になれません。ひきこもりの人も。
大切なのは、子どものときから、可能な限り小さい頃から、仲間と何かに熱中して取り組むことです。熱中するというのは、何かに期待している、希望をもっているときで、子どもは発達することになる、もう少し上手になるのです。木登りやなわとびがもっとうまく、自転車に乗るのがもっと上手に、野球がもっとうまくなるようになる。何でもいいんですが、自分で自分に期待をしているんです。
ビゴツキー(※)がよく言いました。専門家が使う言葉は堅い言葉ですが、「発達方向に向かっての最近接領域の課題を達成しようとしている」と。こんな難しい言葉を使わなくてもいいと思うんですがね。発達方向に向けて、最も近い領域の課題を達成しようとしていると。こうとしか翻訳できないような難しい言葉です。今できないことを、次の段階のことをしようとしている、ということです。
人間というのは、ある意味でいつもそうなんです。それを子どもは遊びの中でしようとしていると。だから遊んでいる子どもを見るとよくわかります。快楽を楽しんでいるんじゃないんです。単に楽しんでいるのではなく、むしろ苦しんでいる。子どもが本当に生き生きと遊んでいるときは、たいてい苦しさにゆがんだ顔をしています。もうこれ以上走れない、という顔をしている。鬼ごっこで鬼にされてしまう瞬間というのは、もうこれ以上走れないからつかまるわけです。木登りをするときは、僕はもうこれ以上怖くて登れない、というところまで登るんです。もっと高く登れる友達がいると、残念だな、うらやましいなと思う。サッカーをするにしても、泳ぐにしても、何をするにしても、ぎりぎりのところを一生懸命努力して、自分を開拓しようとしている。そういうことを仲間と共感しあって熱中しているときに、子どもは最も意欲的だと言えるのです。
●子どもとして意味のあること
逆に、大人が価値を認めるようなことに取り組ませようとするときは、子どもは意欲を示さないんですよね。大人とは価値が違うのです。だけど、子どもが何かに意欲的に取り組もうとしているときは、子どもとして意味のあることをやっているわけです。
育児や教育の失敗というのは、子どもとして意味のあることを省略してしまって、大人が意味を感じることをやらせてしまおうとするときです。親はこういう過ちをしばしばやるんです。その過ちを修正してくれるのは、親以外の人であるときが多いです。となりのおばさんとか、おじいさんとかおばあさんとか、親戚のおじさんとか、その子どもの将来に何かを期待していない人ほど、うまくやってくれます。子どもの将来に何かを期待している人ほど、間違いが多いわけですよね。子どもとして意味のあることに熱中してから、そのあとにだんだん大人の価値観に入り込んでくるといいましょうか。最初の部分を省略してしまってはだめなのです。
では仲間と熱中して何かができるためには、何が必要でしょうか。大田区の児童館の児童指導員の人が、何年も前ですが、朝日新聞の家庭欄に大きな記事を書いていました。今の子どもは、場所と時間と仲間を寄せ集めてあげても遊べない。だから、子どもを指導する指導員が必要なのだと。遊べないんです。なにがいちばんだめかというと、仲間と共感できない。仲間同士が響きあえないんです。ということは、仲間を信じられないわけでしょ。仲間に安心できないのです。これが大きな問題です。時間や場所や仲間を集められても遊べない。実に深刻な問題だと書かれていました。
●信じるのは自分を保護してくれる人
仲間と何かに熱中するには、仲間を信じられるような子どもに育てておかなければならないのです。でも、いきなり仲間を信じられるような子というのは、絶対いないんですよね。子どもの発達の順序からいって、まず、親を信じるところから始まるわけでしょ。あるいは、親代わりの人をね。要するに、自分を保護してくれる人を信じるわけです。ですから、充分に保護された経験をもっている子が、友達との遊びが上手なんです。保護されるということは、自分が困ったときにはいつでも手助けをしてくれる、何かをしてもらえるということです。
私たちが海外に行ったとき、いちばん力になってくれるのは、一般論的にいって日本大使館ですね。飛行機やバスの事故などがあったときに、まず大使館は事故にまきこまれた人の中に、日本の名前の人がいなかったかどうかを調べてくれるでしょう。それが大使館の大きな役割のひとつで、外国に行ったときの私たちの保護者です。その保護してもらう対象であることを証明するために、パスポートというものがあるわけです。困ったときに保護してくれるのです。
ですから、優れた親は、そういうメッセージを子どもによく与えている親ですよね。いちばんだめな親は、親の面子をつぶされることに最もイライラする親。非行少年の親は、ほとんど例外なくそうだと言われます。少年たちがあれこれいう言葉の中に、親の顔に泥を塗るとか、親の面子をつぶしたとか、親に恥をかかせたとかあって、こういうことに対して親は非常に神経質になっていらだつ。保護者じゃないわけです。子どもが親を保護しているようなものでしょ。親の面子をいつも立てようとしている。親を悲しませないように、親を苦しめないようにしようとしている。反社会的な行動をとる非行少年はこうだとずっと考えられてきました。
ところが、今では非社会的な行動をとる子もほとんどそうだと言われるようになりました。社会的な行動がとれない子は、そういうところがあるわけです。保護者が本当の意味で保護の役割をしていないのです。安心していればいいよ、親が矢面に立ってあげるから、ということですよね。親が矢面に立ってあげるから、近所の人に多少の後ろ指をさされても平気だと、困ったときはすぐに家に帰ってくるんだ、保護してあげるからと、こういうことですよね。こういうメッセージを子どもにゆっくりと充分に伝えるということが、本当は最も親として重大な役割です。
●子どもの中の被保護感
こんなことをかつての親は強く意識していたとは思えません。でも、かつては自然な感情としてもっていたわけです。そういう感情を祖父母までもっていた。祖父母の面子ということは、ほとんど言わなかった。親よりも言わなかった。そういう祖父母に守られるところもあったわけです、孫たちは。親では充分でないところを、父母が守ってくれた。二重三重の構造で守られていたところがありました。それから、私たちの村の子どもだから、と村の人が守ってくれたところもありますね。隣のまちで不祥事を起こしたとき、村の人が守ってくれたという地域社会があったわけです。そういうものが充分あったとき、そういう人たちを子どもたちはいろいろな程度に信じることができた。ということは、依存ということです。
依存と信頼というのは、ほとんど同じです。親にどのくらい依存できるか。依存の欲求を満たしてあげるのが、保護です。親は教育者ではないのです。教育者がしばしば自分の子どもの育児に失敗してしまうのは、教育者はいても、いわゆる保護者がいない環境で子どもが育ってしまうことがあり得るからです。教育者でなくても、親たちが教育者のような振る舞いをしてしまう。それを修正したり、補充してくれる人がいない核家族というのも不幸ですね。しかも地域社会がないところで育っていると、地域社会も守ってくれない。こういう状態で育てられると、子どもたちは健全な依存ができない。
被保護感と言います。充分に保護されているという実感がない。依存できる、保護されているという感じが、自分は大切にされているという実感を子どもに与えるわけですよね。自分が大切にされているという実感を持つことによって、自信を持つわけです。だけどその自信より先に、自分を大切に保護してくれる人たちを子どもたちは信じるのです。だから、人を信じることと自分を信じること、人を信じることと健全な自尊心を持つということは同じだと言われるわけです。非行少年に自尊心はないと言われますね。凶悪な犯罪を犯してしまう少年ほど、自尊心を持っていない。自尊心は育てられるどころか、壊されているのです。
●自分が肯定できる他者に出会う
そのように人を信じるとか、自分を信じるとか、自尊の感情とか、他者を尊重するとか、そういうふうに育てられている感情があるから、人に共感できるわけです。共感できるから、友だちができるわけでしょ。友だちができるから、仲間と何かに熱中できるのです。こういう筋道で子どもが育てられてきてほしいと思います。ですから、子どもは何でもかんでも、放っておいて遊べるわけではないんですよ。心をかけて育てられた子が、そういう子ども同士で遊べるんです。このことを私たちは大切にしなければいけないと思いますね。
本当はこういう感情は、そんなに勉強してやることではなくて、子どもが泣いたらあやしてあげたり、おっぱいをほしがったらおっぱいをあげたり、忙しくて子どもから目を離せないときは仕方なくおんぶをしながら野良仕事や洗濯をしていたような時代には、子どもはそういう感情を自然に育てられていたんですよね。親がそんなに計画的に意識的にしなくても。いつも、親の体のぬくもりや祖父母の心が届くところで育てられていて、うまくいっていたという時代がありました。そういう自分というのが自分です。そういう自分がないというのは、自分がないということ。本来は自然にできたものが、自然でなくなったときにどういうふうになるか。専門家はすでに研究していたのですね。
それが時々ご紹介するH・ワロン(※)です。人間はどのようにして私になっていくのか、誇りのある自分というものをどう自分の中に育てていくのかというプロセスを、とても克明に研究した人です。一言で言うと、それは肯定的な他者に出会うこと。他者があって、自分がある。ワロンはそう結論しました。長い生涯をかけて、人間はどのようなプロセスをたどって私になっていくのかを研究しました。そして、どんな個性、能力、特性があるにせよないにせよ、自分というものに肯定的な感情を、私はこれでいいんだという気持ちをどのように育てていくのかは、自分が肯定できる相手に出会うことなしには、どんな方法をとってもだめなんだと言った。その筋道を発見していったわけです。(以下省略)
子育て協会「続・佐々木ノート」№30、2003より
(※) L.ビゴツキー(1896-1934) 旧ソ連の心理学者,児童学者。発達心理や児童心理、言語心理学の分野で独自の理論を展開し、ソビエト心理学の基礎を作る。「児童の言語・思考の発達」を研究し続けた人物で、その思想は21世紀の今日も影響力を持ち続けている。発達理論で「発達の最近接領域」が有名。
H.ワロン (1879-1962) フランスの精神科医、発達心理学者。
無断転用、引用をお断りします。
copyright 佐々木正美